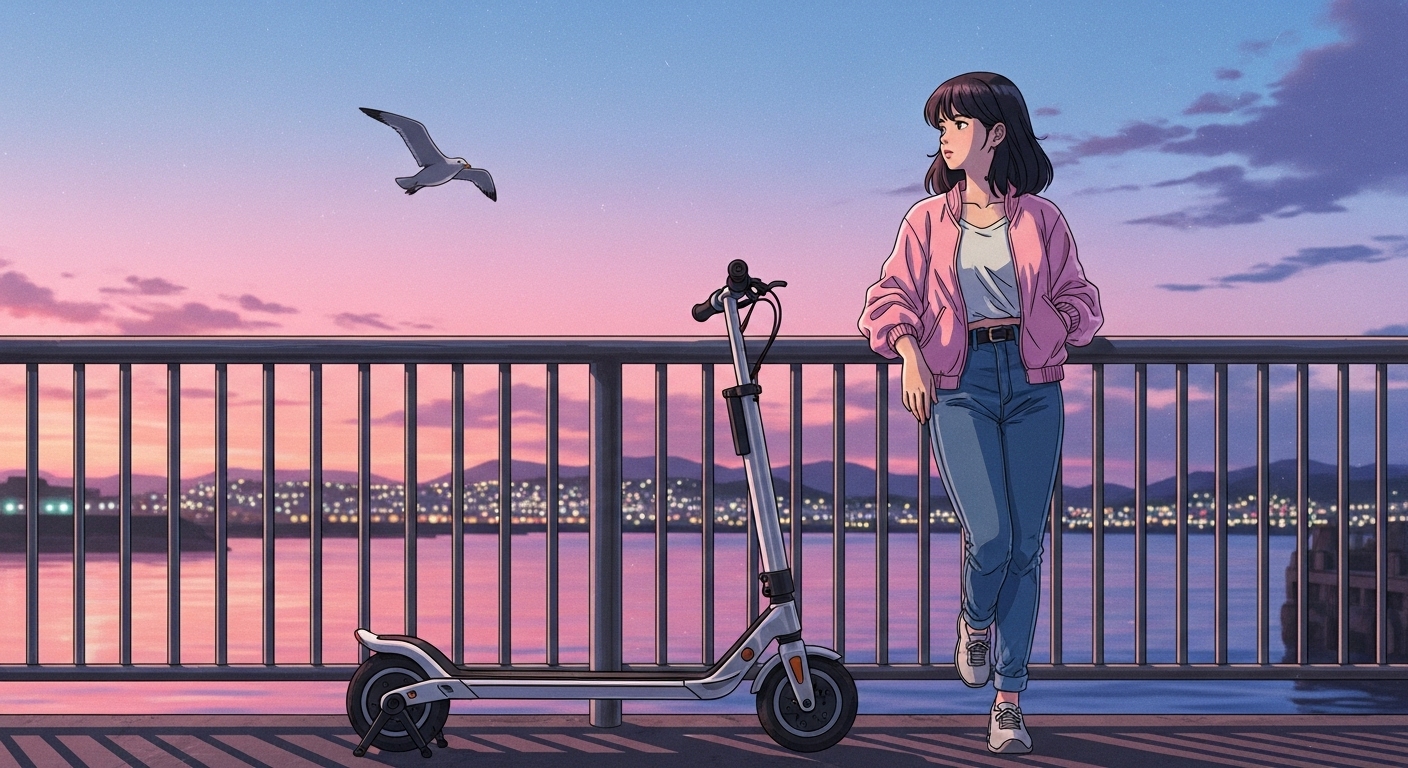
「天気の良い日に、子供やパートナーと電動キックボードで二人乗りできたら気持ちよさそう…」
そんな風に考える方もいらっしゃるかもしれません。手軽で便利な特定原付(電動キックボード)ですが、もし二人乗りを考えているなら、絶対にやめてください。結論から言うと、特定原付の二人乗りは明確な法律違反であり、重大な事故につながる非常に危険な行為です。
この記事では、なぜ二人乗りが禁止されているのか、その法的根拠と罰則、そして「原付二種なら二人乗りできる」という話の真相まで、法律と特定原付に精通した専門家の視点から徹底的に解説します。
この記事を読めば、二人乗りに関する疑問がすべて解消され、安全に電動キックボードを楽しむための正しい知識が身につきます。
※この記事には広告が含まれています。
目次
この記事の要点まとめ
- 特定原付の二人乗りは「定員外乗車違反」という交通違反です。
- 違反した場合、反則金5,000円または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- 子供との二人乗りも、親子タンデムも、例外なく全て禁止されています。
- 「原付二種」区分の電動モビリティであれば、条件付きで二人乗りが可能です。
結論:電動キックボード(特定原付)の二人乗りは法律違反です
特定小型原動機付自転車(特定原付)に関する交通ルールは、2023年7月1日に施行された改正道路交通法によって定められています。この法令に基づき、二人乗りは厳しく禁止されています。
なぜ禁止?根拠は道路交通法
電動キックボード、特に2023年7月1日から新設された「特定小型原動機付自転車(特定原付)」の乗車定員は、法律で1名と定められています。これは道路交通法第五十七条で定められており、二人乗りは「定員外乗車」という明確な違反行為にあたります。
第五十七条 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁の公式サイトでも、特定原付の交通ルールとして「二人乗りの禁止」が明記されています。これは安全に走行するための絶対的なルールであり、例外はありません。「ちょっとそこまでだから」「子供が小さいから」といった理由は一切通用しないのです。
特定原付の車体は、そもそも一人で乗ることを前提に設計されています。ブレーキ性能、フレームの強度、重心バランスなど、すべてが一人乗りに最適化されています。ここに二人目が乗ると、車両の性能限界を超えてしまい、ブレーキが効きにくくなったり、バランスを崩して転倒しやすくなったりと、非常に危険な状態になります。
違反した場合の罰則は?「定員外乗車違反」について
もし電動キックボードで二人乗りをして警察官に見つかった場合、「定員外乗車違反」として交通反則切符(青切符)が交付されます。特定原付の場合、この違反には反則金5,000円が科せられます。
さらに、交通反則通告制度が適用されない場合や、悪質な違反と判断された場合は、刑事罰の対象となり、5万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第121条第1項第5号)。
| 違反行為 | 反則金(行政罰) | 罰金(刑事罰の上限) |
|---|---|---|
| 定員外乗車違反 | 5,000円 | 5万円以下 |
「5,000円なら…」と安易に考えてはいけません。最も重い罰則は、事故を起こしてしまった場合です。二人乗りによる事故で相手に怪我をさせてしまった場合、運転者には重い行政処分や刑事罰が科される可能性があります。また、自賠責保険は適用される可能性がありますが、任意保険では「法令違反」を理由に保険金が支払われないケースも考えられます。軽い気持ちで行った二人乗りが、人生を左右するほどの大きな代償につながる可能性があることを、絶対に忘れないでください。
シェアサービス(LUUPなど)も二人乗りは厳禁
街中でよく見かけるLUUP(ループ)などの電動キックボードシェアリングサービスも、当然ながら二人乗りは固く禁止されています。 各サービスの利用規約で明確に禁止されており、違反が発覚した場合はアカウントの停止や罰金などのペナルティが科される可能性があります。
特に、シェアサービスは多くの人の目に触れるため、二人乗りをしていると他の利用者や歩行者から通報されるケースも少なくありません。実際にSNSなどでは「LUUPで二人乗りしている人を通報した」といった投稿も見られます。自分たちの利用だけでなく、サービス全体のイメージを損ない、ルールを守っている他の利用者の迷惑にもなる行為です。軽い気持ちでルールを破ることは、絶対にあってはなりません。
「子供と一緒なら…」もNG!二人乗りの危険性
なぜ子供との二人乗りもダメなのか?
「小さな子供を前に乗せるくらいなら大丈夫だろう」と考えるのは、非常に危険な誤解です。法律上、乗車定員は年齢に関係なく「1名」です。つまり、たとえ幼児であっても、二人乗りは違反となります。
法律的な問題以上に、子供との二人乗りには深刻な安全上のリスクが伴います。子供は予測不能な動きをすることがあります。急に体を動かしたり、ハンドルに手を伸ばしたりすることで、運転者は簡単にバランスを崩してしまいます。また、事故で転倒した際、子供は大人よりも大きなダメージを受けやすく、特に頭部を強打すれば命に関わる事態になりかねません。ヘルメットの着用が努力義務である特定原付ですが、万が一の際に無防備な子供を危険に晒す行為は、保護者として絶対にあってはなりません。大切な子供の命を守るためにも、子供との二人乗りは絶対にやめましょう。
車両構造から見る二人乗りのリスク
特定原付がなぜ一人乗り専用なのかは、その構造を見れば明らかです。二人乗りをすることで、具体的にどのようなリスクが発生するのかを理解しておきましょう。
- ブレーキ性能の低下: 特定原付のブレーキは、運転者1名の体重を前提に設計されています。体重が倍近くになれば、制動距離(ブレーキが効き始めてから完全に停止するまでの距離)は大幅に長くなります。危険を察知してブレーキをかけても間に合わず、追突事故などを起こすリスクが格段に高まります。
- 重心の不安定化: 二人乗りをすると、本来の設計とは異なる高い位置に重心が移動します。これにより、車体は非常に不安定になります。特にカーブや段差ではバランスを崩しやすく、簡単に転倒してしまいます。
- フレームやタイヤへの過負荷: 車両には最大積載重量が定められています。二人乗りはこの重量をオーバーする可能性が高く、フレームの破損やタイヤのパンクといった物理的な故障を引き起こす原因となります。走行中に突然車体が壊れることを想像してみてください。その危険性は計り知れません。
これらのリスクは、運転者だけでなく同乗者、そして周囲の歩行者や他の車両をも巻き込む大事故につながる可能性があります。「少しだけなら」という油断が、取り返しのつかない結果を招くのです。
例外はある?二人乗りできる電動モビリティとは
「原付二種」区分の電動キックボード・バイクなら可能
「どうしても二人乗りがしたい」というニーズに応える選択肢が、実は存在します。それは、「原付二種(第二種原動機付自転車)」に分類される電動キックボードや電動バイクです。
これらはモーターの定格出力が0.6kW超〜1.0kW以下の車両で、法律上は51cc〜125ccのバイクと同じ扱いです。原付二種の車両には、タンデムステップ(同乗者の足置き)やシート、グラブバーなど、二人乗りに必要な装備が備わっているモデルがあり、これらの条件を満たしていれば合法的に二人乗りをすることが可能です。
ただし、誰でもすぐに二人乗りができるわけではありません。運転者は、普通自動二輪免許(小型限定以上)を取得してから1年以上経過している必要があります。これは、運転に慣れていないライダーが二人乗りをすることの危険性を考慮したルールです。免許の条件を満たさずに二人乗りをすると『大型自動二輪車等乗車方法違反』となり、反則金12,000円(違反点数2点)が科せられます。
特定原付と原付二種の違い
手軽な特定原付と、パワフルで二人乗りも可能な原付二種。両者には大きな違いがあります。ライフスタイルに合わせて選ぶためにも、その違いをしっかり理解しておきましょう。
| 特定小型原動機付自転車 | 原付二種 | |
|---|---|---|
| 免許 | 不要(16歳以上) | 必要(小型限定普通二輪免許以上) |
| ヘルメット | 努力義務 | 着用義務 |
| 最高速度 | 20km/h | 60km/h(法定速度) |
| 二人乗り | 不可(定員1名) | 可能(運転経験1年以上の条件あり) |
| ナンバープレート | 専用の小型サイズ | ピンク色 |
| 自賠責保険 | 加入義務あり | 加入義務あり |
| 二段階右折 | 不要 | 不要 |
このように、原付二種は特定原付に比べてパワフルで利便性が高い一方、運転免許やヘルメットの着用義務など、守るべきルールも厳しくなります。もし二人乗りを主目的として電動モビリティの購入を検討する場合は、これらの条件をすべてクリアできるかを確認した上で、原付二種モデルを選ぶ必要があります。
特定原付に関するよくある質問(FAQ)
Q. 電動キックボードを押して歩く場合、子供を乗せてもいいですか?
A. 電源を切り、完全に手で押して歩いている状態であれば、法律上は「歩行者」の扱いとなります。このため、車両に乗っているとは見なされず、定員外乗車の違反には問われない可能性が高いです。しかし、安全性の観点からは推奨できません。バランスを崩して転倒し、お子さんが怪我をするリスクは依然として残ります。また、誤って電源が入ってしまう可能性もゼロではありません。基本的には、乗車しない時もお子さんを乗せるのは避けるべきです。
Q. 二人乗りしている人を見かけたら通報すべきですか?
A. 二人乗りは非常に危険な違反行為であり、事故を未然に防ぐという意味では、警察(110番)に通報することも一つの選択肢です。ただし、直接注意することはトラブルの原因にもなりかねないので避けましょう。場所や時間、車両の特徴などを伝えれば、警察がパトロールを強化するなどの対応をとってくれる場合があります。特にLUUPなどのシェアサービスの場合は、サービス提供会社のカスタマーサポートに報告することで、違反者への警告やアカウント停止などの措置がとられることもあります。
Q. 原付二種の電動キックボードで二人乗りする際の注意点は?
A. まず、運転者が小型限定以上の二輪免許を取得後1年以上経過していることが絶対条件です。その上で、運転者・同乗者ともにヘルメットを必ず着用してください。また、二人乗りをすると一人乗りの時とは運転感覚が大きく変わります。急発進・急ブレーキ・急ハンドルを避け、いつも以上に慎重な運転を心がけましょう。乗車前には、タイヤの空気圧やブレーキの効きを必ず点検することも重要です。
Q. 自転車の二人乗りとはルールが違うのですか?
A. はい、全く違います。自転車は「軽車両」に分類され、一定の条件(幼児用座席の設置、運転者の年齢など)を満たせば幼児を乗せることが許可されています。一方、特定原付は「原動機付自転車」の一種であり、乗車定員は1名と厳格に定められています。自転車と同じ感覚で「子供を乗せても大丈夫だろう」と考えるのは間違いですので、絶対にやめてください。
まとめ:ルールを守って安全に電動キックボードを楽しもう
今回は、電動キックボードの二人乗りについて解説しました。重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 特定原付の二人乗りは法律で禁止された「定員外乗車違反」(定員1名)
- 違反すると反則金5,000円、または5万円以下の罰金が科される
- 子供との二人乗りも例外なく禁止
- 二人乗りをしたい場合は、運転経験などの条件を満たした上で「原付二種」モデルを選ぶ必要がある
電動キックボードは、正しく使えば日々の移動をとても便利で楽しいものにしてくれる素晴らしい乗り物です。しかし、その手軽さゆえに、ついルールを軽視してしまいがちです。二人乗りという一つの違反行為が、あなた自身だけでなく、大切な同乗者や周囲の人々を不幸な事故に巻き込む可能性があります。
必ず一人で乗車するという絶対的なルールを守り、安全に電動キックボードライフを楽しんでください。
安全な一人乗りを楽しむための特定原付選びについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
特定小型原動機付自転車についての外部リンク
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車について(経済産業省)
- 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)(国土交通省)
- ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF)(国土交通省)
- 電動キックボード等の概要説明リーフレット(PDF)(警視庁)
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
- 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!(政府広報オンライン)
- 電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!(政府広報オンライン)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)


